- 「2歳児が手づかみ食べに戻る理由は?」
- 「3歳目前の2歳児が手づかみ食べに戻った!!何歳までなら良い?」
- 「2歳児に実践して効果があった手づかみ食べの対策が知りたい!!」
スプーンやフォークを使って上手に食べていた2歳児が突然手づかみ食べに戻ってしまい、スプーンを使う様子がないと手づかみ食べのままで良いのかなと不安になってしまいますね。

実は手づかみ食べのままで良いんです!
しかし、
- 「後片付けが大変だから」
- 「ほかの子ができてるから」
といった理由で無理やりやめさせると子どもの心と身体の成長に悪影響を与える可能性があります。
なぜなら、手づかみ食べを1日3回の食事で何度も𠮟っていると子どもにとって「食事は楽しくないもの」になり、食べる量が減って身体の成長に悪影響を与えるからです。
美味しい食事を用意しても子どもが悲しそうに食べていたら、ママパパも気になって食事の味なんてわからなくなりますよね。
そこで今回、2歳児を育てた経験をもつ私が実体験をもとに、2歳児が手づかみ食べに戻ってしまう理由やスプーンやフォークを使ってもらえる方法を解説します。
- 「2歳児が手づかみ食べに戻る理由がわかる」
- 「何歳まで手づかみ食べをして良いかがわかる」
- 「2歳児に実践して効果があった手づかみ食べ対策がわかる」
この記事を読むと、2歳児の手づかみ食べが再開してしまい、ひとりで悩んでいたあなたの気持ちが晴れて子どもと楽しい食事の日々を送れるようになります。
2歳児が手づかみ食べに戻ってしまう理由

2歳児が手づかみ食べに戻ってしまう理由は、まだ理性が未発達で本能や欲望で行動をおこすからです。
例えば、
- 2歳児の前に大好きなホットケーキを置く
- 「ママも椅子に座ったら一緒に食べようね」と言う
- 子どもは我慢できずにホットケーキをもぐもぐ食べ始める
というように、2歳の子はまだ理性が未発達で「やりたい」と思ったことはすぐに実行したくなります。
他にも、スプーンやフォークに見慣れて興味を失ったり、スプーンやフォークを使って食べてもママパパが褒めてくれないことも理由に考えられます。

そういえば息子くんが上手にスプーン使って食べても褒めてなかったかも⁉

自分の食事に集中したり、後片付けとかしてると見逃しちゃうよね
手づかみ食べは3歳を目安にやめさせるのが理想

手づかみ食べは3歳を過ぎたら少しづつやめさせることが理想です。
3歳以降に子どもの理性が徐々に育っていき、理性>本能になる可能性が出てくるので、
手づかみ食べ卒業を目指して準備を始めましょう。
手づかみ食べ卒業を目指すときの3つの注意点
手づかみ食べの卒業を目指すときは、以下の3つの注意点に気をつけましょう。
- 個人差があるので、ほかの子と比較しない
- 3歳すぎたからと無理やりにやめさせない
- 子どもに食事=怖いものとイメージを作らないよう怒鳴ったりしない

うーん…わかっているつもりだけど、スプーン投げたりしたらつい怒鳴っちゃう

そうだよね!ママパパだって神様じゃないから完璧を目指さなくて良いよ!
あなたにとってできる範囲で楽しく子育てするのがベストだよ!!
2歳児にスプーン・フォーク・箸を使ってもらう7つの方法

次に2歳児にスプーン・フォーク・箸を使ってもらう7つの方法を紹介します。
- 使わなくても食膳に出す
- レストランごっこなどで遊びに取り入れる
- ママパパがカトラリーや箸を使っている姿を何度も見せる
- カトラリーや箸が出てくる絵本を読み聞かせてみる
- 今まで使ったことがない新しいカトラリーで興味をひく
- ママパパがカトラリーや箸に声をあててキャラクター化して親しみを持たせる
- それぞれ使いやすい食材で練習する
それぞれ詳しく解説していきますね。
①使わなくても食膳に出す
スプーンやフォーク、箸を使っても使わなくても良いので、食膳に出します。
毎日、子どもに見せることで警戒心をなくし、ふと興味が出て「触ってみよう!」と思う日が必ずあります。そこで、あれこれと口を出さずに見守ります。
すると、子どもから「どうやって使うの?」と聞いてきたら教えてあげます。
もちろん、聞く前にうまく使えず泣いてしまうこともありますが、「使ってみたかったんだね」と
子どもの気持ちに寄り添いながら使い方を教えてあげましょう。

息子が箸に興味出して触ろうとしたときに、つい口出したら怒られちゃった…

使い方が間違ってても、最初は教えたい気持ちをグッとこらえて見守ってあげてね!
②レストランごっこなどで遊びに取り入れる
おもちゃのスプーンやフォークで子どもと一緒に食べる動作をして遊びましょう。
プラスチックのお皿におもちゃの人参やトマトを乗せて落とさないように運んだりすると、
遊びが本番の時の食事で活きてきます。

今までパクパク~って簡単にやってたけど、意味があったんだね!

そうだよ!子どもは遊びからたくさんのことを学んでいるよ!
③ママパパがカトラリーや箸を使っている姿を何度も見せる
離乳食の頃からママパパがスプーンなどや箸を使っている姿を見せてあげましょう。

食事中にチラッと息子を見てもパパが箸持ってるとき全然見てないよ。効果あるの?

パパが気づかない時に見ているよ!
ちゃんと見てほしい時は、これスプーンで食べると美味しいねって声かけると良いかも!!

そっか…それぞれ黙々と食べちゃうとパパも息子くんのこと見てないかも

子どもに話しかけながらの食事は時間やママパパの心に余裕も必要だから
毎日じゃなくて気が向いた時にやってみよう!
④カトラリーや箸が出てくる絵本を読み聞かせてみる
スプーンやフォーク、箸が出てくる絵本を読み聞かせて使い方を教えてあげましょう。
絵本のキャラクターが楽しそうにホットケーキを食べる姿を見て、子どもに「楽しそうだな!」「使ってみたい!」という気持ちを持たせます。
また、読み終えたあとに絵本と同じ食べ物をフォークやスプーン、箸で食べることも効果的です。

絵本に出てくる食べ物ってとても美味しそうに見えるよね~!!

そうそう!私も小さいころ、お菓子作る絵本が大好きだった!
⑤今まで使ったことがないカトラリーで興味をひく
今まで使ったことがないスプーンやフォーク、箸を用意して興味をひいてみましょう。
子どもは「新しいもの」が大好きなので、お店で子どもに新しいスプーンを選んで買ったり、ママパパだけが使っていたカトラリーを食膳に出してあげると良いです。

パパの箸使う~って泣かれたことがあるから興味ありそうだね!

大人の長い箸を子どもが触るときは近くで見守ってあげよう!
⑥ママパパがカトラリーや箸に声をあててキャラクター化して親しみを持たせる
子どもがカトラリーにまったく興味を持ってくれない時はママパパが声をあててキャラクター化してみましょう。
たとえば、
スプーンを縦に持って少し離れたところからチョコチョコと歩いてくるように上下させ、「〇〇くん、こんにちは!」と子どもの名前を読んで挨拶すると、子どもは嬉しそうにニヤニヤしながら興味を持ってくれます。

この前、大泣きしてるときにやったらスプーン取られて投げられたよ…

それはタイミングが悪かったね…なるべく子どもの機嫌が良さそうなときにやったほうが良いよ!
⑦それぞれ使いやすい食材で練習する
カトラリーや箸が使いやすい食材を用意して練習させてあげましょう。
以下が使いやすい食材とポイントの一覧です。
- スプーン
食材…ポタージュ、ヨーグルト、ゼリー、プリン
ポイント…とろみがあって手づかみできないものが良い - フォーク
食材…ゆでた人参・大根など、麺類
ポイント…厚さは5㎜~1㎝、子どもの一口で食べられる長さ - 箸
食材…ゆでブロッコリー・キャベツ、高野豆腐、マカロニ
ポイント…あんかけなどでとろみをつけてしまうと滑りやすい
ちなみに、2歳児が使いやすいカトラリーと箸の選び方は以下の通りです。
- スプーン…すくう部分が子どもの口3分の2くらいの大きさで、細く深さがあるもの。
- フォーク…刺す部分が細く、丸みがあるもの。先がとがっているものは避ける。
- 箸…長さが短く、先がとがってなく、滑り止めがあるもの。
- 皿…深さがあり、縁が直角のもの。縁がなだらかなものはすくいにくい。

最初はフォークの刺す部分、こわいって言ってたね

そうだね。今は慣れてきて気にせずに使ってくれてるよ
食べこぼしの片づけにうんざりしない対策10選

手づかみ食べ卒業までの道のりは長いので、食後の後片付けを少しでも簡単にする対策を10選ご紹介します。
- 深く広いトレーを使う
⇒食べこぼしが広がらない - ポケット付きのエプロンを使う
⇒口からこぼれたものをキャッチしてくれる - 吸盤付きのプラスチック食器に変える
⇒ひっくり返したり、ぶつかっても中身がこぼれない - 重めのワンプレートで用意する
⇒ひっくり返されず、一度の配膳で準備ができる - テーブルの上にウェットシートを常備
⇒汚れたらすぐに拭ける - 子どもの椅子はシンプルなものを選ぶ
⇒形がシンプルだと汚れたときに掃除しやすい - 子ども椅子のクッションは洗えるものにする
⇒汁物がこぼれたとき、洗濯できる - 壁にビニールシートを貼る
⇒手についた汁を飛ばしてもすぐに拭ける - 子ども椅子の下に新聞紙やビニールシートを敷く
⇒食べこぼしが椅子より下に落ちてもすぐ拭きとれる - 周囲に何も置かない
⇒投げられた食材がすぐに見つかり掃除できる
我が家で重めのプレートはこれを使用していました。
3か所に、子どもに与えたい栄養の主食(炭水化物)、主菜(たんぱく質)、副菜(野菜)がそれぞれ入れられるので栄養バランスを意識しやすかったです。
なにより、こぼしてもプレートがキャッチしてくれるので片付けが楽になって助かりました。

これで結構掃除しやすくなったよね!

そうそう!1日2回~3回も後片付けがあるから少しでも負担を軽くしよう!

そういえばトレーを使っていたら引っ張られて悲惨な目にあったんだけど、何か方法ある?

トレーの裏に滑り止めをつけると良いよ!100均の剥がせるテープとかオススメだよ!
我が家で効果があったスプーンやフォーク、箸のススメ方を3つ紹介!

最後に、我が家で試してみて効果があったカトラリーや箸のススメ方を3つ紹介します。
- スプーンで食べやすい大好きなものを繰り返し食べさせる
- 複数用意したスプーンをローテーションで食膳に出す
- コンビニ等でもらえるスプーンやフォークで一緒に遊ぶ
プラスチックのスプーンやフォークは、2歳の噛む力で割れて破片を飲み込んでしまう場合があるので、目の届く範囲で遊ばせましょう。
◆もしもプラスチックの破片を飲み込んでしまったら
いつもと違う様子はありませんか。「顔色」「機嫌」「元気」はどうでしょうか。
引用:あいち小児保健医療総合センター
もし変わりなければ様子を見て便から排泄されるのを待って大丈夫です。

息子くんの大好きなものがヨーグルトだったので毎日食卓に出してスプーン練習しました!

フォークと箸が使いやすい食材はつかみ食べしやすい食材でもあるから練習はしづらいね…

そうなんだよね…!フォークはパスタでくるくるしたり、箸は遊びで少しずつ練習するのが良いかも!
まとめ
◆2歳児が手づかみ食べに戻ってしまう理由
理性が未発達で本能や欲望で行動するから
◆手づかみ食べは3歳を目安にやめさせるのが理想
3歳以降から少しずつ手づかみ食べ卒業の準備をする
◆手づかみ食べ卒業の3つの注意点
- 個人差があるので、ほかの子と比較しない
- 3歳すぎたからと無理やりにやめさせない
- 子どもに食事=怖いものとイメージを作らないよう怒鳴ったりしない
◆カトラリーや箸を使ってもらう7つの方法
- 使わなくても食膳に出す
- レストランごっこなどで遊びに取り入れる
- ママパパがカトラリーや箸を使っている姿を何度も見せる
- カトラリーや箸が出てくる絵本を読み聞かせてみる
- 今まで使ったことがないカトラリーで興味をひく
- ママパパがカトラリーや箸に声をあててキャラクター化して親しみを持たせる
- それぞれ使いやすい食材で練習する
◆カトラリーや箸が使いやすい食材とポイント
- スプーン
食材…ポタージュ、ヨーグルト、ゼリー、プリン
ポイント…とろみがあって手づかみできないものが良い - フォーク
食材…ゆでた人参・大根など、麺類
ポイント…厚さは5㎜~1㎝、子どもの一口で食べられる長さ - 箸
食材…ゆでブロッコリー・キャベツ、高野豆腐、マカロニ
ポイント…あんかけなどでとろみをつけてしまうと滑りやすい
◆手づかみ食べの後片付けを簡単にする対策10選
- 深く広いトレーを使う
⇒食べこぼしが広がらない - ポケット付きのエプロンを使う
⇒口からこぼれたものをキャッチしてくれる - 吸盤付きのプラスチック食器に変える
⇒ひっくり返したり、ぶつかっても中身がこぼれない - 重めのワンプレートで用意する
⇒ひっくり返されず、一度の配膳で準備ができる - テーブルの上にウェットシートを常備
⇒汚れたらすぐに拭ける - 子どもの椅子はシンプルなものを選ぶ
⇒形がシンプルだと汚れたときに掃除しやすい - 子ども椅子のクッションは洗えるものにする
⇒汁物がこぼれたとき、洗濯できる - 壁にビニールシートを貼る
⇒手についた汁を飛ばしてもすぐに拭ける - 子ども椅子の下に新聞紙やビニールシートを敷く
⇒食べこぼしが椅子より下に落ちてもすぐ拭きとれる - 周囲に何も置かない
⇒投げられた食材がすぐに見つかり掃除できる
◆試して効果があったカトラリーや箸の3つのススメ方
- スプーンで食べやすい大好きなものを繰り返し食べさせる
- 複数用意したスプーンをローテーションで食膳に出す
- コンビニ等でもらえるスプーンやフォークで一緒に遊ぶ
今回は2歳児の手づかみ食べが戻ってしまったときの原因と対策、実際に試して効果があった方法を紹介しました。
今までスプーンやフォークで上手に食べていたのに、手づかみ食べが再開して後片付けが多くなるとママパパが大変になってしまいますね。
この記事を読んで、子どもの手づかみ食べが戻ってしまったときにあなたの負担が少しでも軽くなる方法が見つかれば幸いです。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
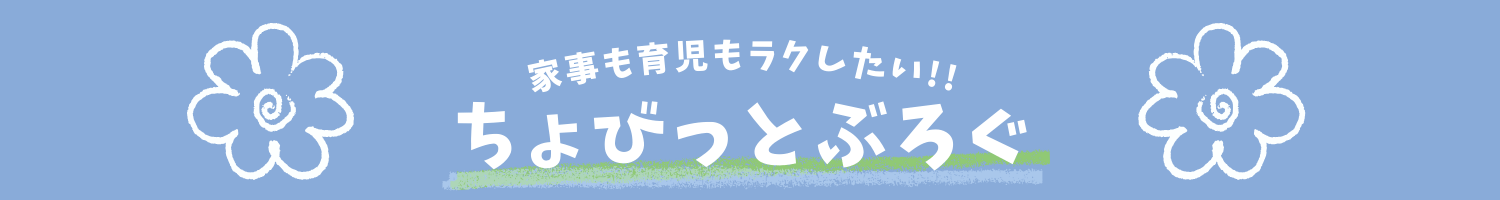
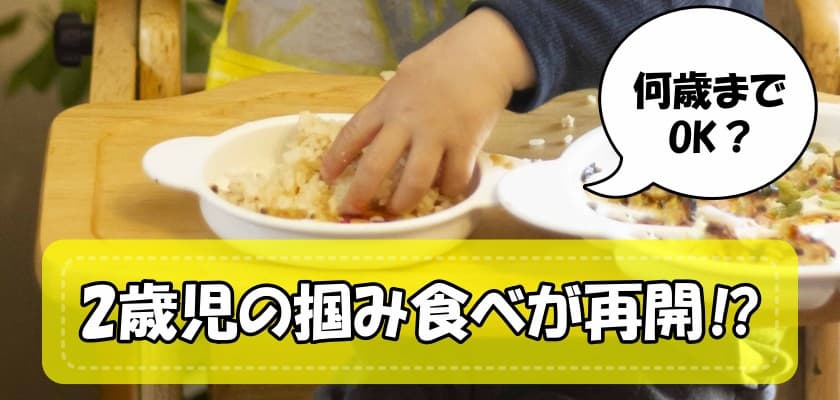
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd747d6.395dd766.4bd747d7.caf6d98b/?me_id=1227615&item_id=10001008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fedute%2Fcabinet%2Fezpz%2Fhappymat_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


